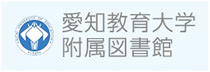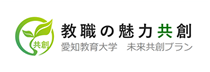臨床心理学コース
臨床心理学コース 令和2年度入学 岩田 倫佳さん
愛知教育大学院に進学した理由を教えてください。
入学前に大学院説明会に参加し、愛知教育大学院が現場志向で実習に力を入れていることを知りました。そして、学内の相談室では不登校や学校不適応、発達障害に関わるケースに触れる機会が多いと聞きました。私は当時、学校現場の心理士に特に興味があったため、充実した教育臨床の実習に魅力を感じていました。心理士はクライエントが抱えている問題を多方面から理解することが求められます。そのためにはさまざまな機関と連携することが必要であり、教育臨床だけではなく、病院臨床や発達・福祉に関する知識も必要です。愛教大の学内には発達支援相談室もあり、発達や福祉に関する学びも得られます。愛知教育大学院を修了された先輩方には病院で働いている方もおり、教育・福祉・医療の全ての領域でより実践的な支援を学ぶことができると考え、進学を希望しました。
研究テーマについて教えてください。
私は、これまで困難な出来事を通じた肯定的な変容に関する研究に興味を持ってきました。修士論文では、より多くの人が経験する対人関係における傷つき体験に着目しています。ネガティブ感情の対処において、認知的感情制御(状況に対する考え方や解釈の変化を通じて、感情の変化が生じる現象)という視点に近年注目が高まっています。認知的感情制御の主な効果は、精神的健康の向上として示されていますが、自己成長感(困難な状況に対する取り組みの結果として得られる心理面の肯定的変化)の獲得にも関連することが実証的に示されています。また、自己成長感はソーシャルサポート(特定個人が、特定の時点で、彼/彼女と関係を有している他者から得ている、有形/無形の諸種の援助)と関連があることが指摘されており、ソーシャルサポートが高いほど自己成長感が高いことが明らかになっています。以上から、修士論文では、認知的感情制御がソーシャルサポートを通じて、自己成長感とどう関連するのかを検討しています。
学部と大学院とで大きく違うと感じることは何ですか。
学べる内容がより専門的になるということです。大学院では、学内相談室にてケースを担当するため、より深くクライエントさんと関わることができます。また、アルバイトや実習においても学部生の時に比べて専門的な機関や仕事に携わることができるため、現場に根ざした、より専門的な勉強ができます。
印象に残っている授業を1つ教えてください。またそれはなぜですか。
臨床心理実習(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)です。この授業では、学内の心理教育相談室の事例について、学生、教員が意見を出し合い検討することが行われます。自分が持っているケースについて、多様な観点から意見をいただくことで、自分にはなかった気付きが得られたり、ケースの振り返りをしたりすることができます。また、院の在籍期間に自分が担当できるケースには限度がありますが、この授業を通して多くの事例に触れることができます。加えて、院の仲間が事例にどのように取り組んでいるのかを知ることができるため、刺激を得る機会にもなります。ケース全体の見立てや方向性についても、先生方が丁寧にコメントをくださるため、とても勉強になります。
修了後は、どんなことにチャレンジしたいですか。(仕事やライフプラン、キャリアプランなど)
大学院での授業や実習を通して幅広い分野に興味を持ちましたが、まずは医療領域で経験を積む予定です。そして、約1年後には臨床心理士試験や公認心理師試験があります。そこでの資格取得を目指して、現場で経験を積みつつ試験対策にも力を入れたいです。大学院の2年間では多くのことを学びましたが、同時に知らないこと、知るべきことがたくさんあることにも気付きました。また、心理士の仕事は社会と密接に関わっており、社会の変化や自分の変化にも常に敏感であることが大切だと感じています。院を修了してからも、さまざまな分野で働く方と交流したり、学会等に参加したりして学び続けていきたいと考えています。
臨床心理学コース 令和3年度入学 山崎 双葉さん
愛知教育大学院に進学した理由を教えてください。
もともと愛知教育大学に通っていたため、慣れ親しんだ環境があることが一番の決め手でした。お世話になっていた先生方から、もっとたくさんのことを学びたいという気持ちも大きかったです。
研究テーマについて教えてください。
研究テーマは心理的に感じる「ゆとり」についてです。ゆとりという言葉を私たちは日常的に口にしますが、ゆとりという言葉が一体何を指しているのかは曖昧な状態にあります。ゆとりは日常場面での適応にも関わってくると考えられます。そこで私は、どんな時にゆとりを感じるのか、ゆとりの感じやすさには個人差があるのかといったことについて研究をすすめています。
学部と大学院とで大きく違うと感じることは何ですか。
学生の主体性です。たった二年しかない大学院ですので、自ら学びを深めようとする姿勢を皆持っています。そのためかなり忙しく凝縮された時間ですが、やりたいことを思う存分に深められるのでとても楽しい時間です。
印象に残っている授業を1つ教えてください。またそれはなぜですか。
事例検討を行う授業です。実際の心理面接について思いを巡らせることができ、自分の考え方の偏りに気づくことで新しい視点を獲得することができます。実際の事例を提供していただけることは貴重ですので、一回一回がとても勉強になります。
修了後は、どんなことにチャレンジしたいですか。(仕事やライフプラン、キャリアプランなど)
修了後には、様々な領域で心理職として仕事を経験してみたいと考えています。大学院で学ぶことと、実際に現場に出てから学ぶことは大きく異なると思います。どちらも経験してから、私自身がどこで専門性を磨いていくのか検討していきたいと考えています。
臨床心理学コース 令和4年度入学 松本 伽音さん
愛知教育大学院に進学した理由を教えてください。
私は、不登校や児童虐待、発達障害など様々な困難さを抱える子どもと家族への心理支援がしたいと考えていました。本学は学内外の実習やケースカンファレンスの体制が充実していることから、クライエントの心理的課題の背景にあるメカニズムや、個別性のある心理支援について実践的に探求できると考えました。また私は、「教育領域における全ての子どもへの予防的な心理支援」に関心があり、子どもが困ったときに大人に助けを求められるような働きかけがしたいと考えていました。本学は教育大学ならではの魅力があり、学校での実習において、臨床心理学を基盤にしながら子どもに近い立場で継続的な関わりができると知り、本学への進学を決めました。
研究テーマについて教えてください。
私は修士論文において、「親の離婚を経験した当事者の別居親(離れて暮らす親)への思いと関係性」について質的に研究しました。7名の当事者にインタビュー調査を行い、複線径路等至性モデル(TEM)を用いて分析しました。別居親との交流が①継続する場合、②中断する場合、③交流がない場合の3つに分けて、それぞれの葛藤や支えについて明らかにした上で、子どもの心理支援の在り方について考察しました。執筆中は指導教員や仲間に支えられ、最終的に紀要論文にも投稿することができました。
大学院生活の中で、印象に残っていることを教えてください。
学内相談室の実習において、仲間と深く語り合うと同時に、学内外の教員のスーパービジョン(SV)を受けられたことが印象に残っています。学内実習では初めてケースを担当し、一人一人のクライエントさんと真摯に向き合うよう努力をしましたが、自分の力量不足を感じ、クライエントさんの役に立つことができてないと思うことも多々ありました。その中で、SV教員から新たな視点を学び感銘を受けたり、温かな励ましに支えられたりすることがありました。加えて、ケースの見立てや支援方針を仲間と真剣に語り合ったことは、自分の未熟さに打ちのめされそうなときの大きな支えとなりました。学問的な知識や理論、技術を実際の現場に活かすことは想像以上に難しいことですが、先生方と仲間の存在により、実習を通して自分の臨床観を育て、心理学的な知識を現場に応用する基盤をつくることができたと思います。
大学院修了後に取得した資格について教えてください。
私は大学院修了後の社会人1年目に臨床心理士の資格を取得しました。私自身は学部で心理学以外の学問を専攻していたことから公認心理師の受験資格はありませんが、資格に関することは先生方に相談していました。
入学を考えている方へのメッセージをお願いします。
修士課程の2年間は心理職の土台をつくる時期であり、その後の自分の心理職としてのスタンスや考え方にも深く関わってくるかと思います。本学は「子どもの臨床」に強く、教育・発達・医療の多方面から、子ども・家族への心理支援について現場に根差して探求できます。また、研究についてもゼミの仲間と意見を交わし、指導教員の丁寧なご指導を受けながら、自分の関心テーマを主体的に掘り下げられる環境があります。そして何より院生同士の対話や修了生との繋がり、先生方への相談のしやすさといったソフト面も、心理職を目指す自分の成長にとっては欠かせなかったと思います。院修了後も仕事で迷ったときは大学院での学びに立ち返ることが多く、大学院での全ての経験が現場の臨床に活きていると実感しています。心理職への熱意があれば、充実した院生活を送ることができると思います。
臨床心理学コース 令和5年度入学 森 愛花さん
愛知教育大学院に進学した理由を教えてください。
私は当時,児童期や青年期のこどもとその保護者に対する支援に関心がありました。愛知教育大学には,家族心理学や社会的養護,学校心理学など,親子支援に関わる分野を専門とする先生方が多くいらっしゃることを知り,進学を希望しました。
研究テーマについて教えてください。
青年期の親子関係について研究を進めています。近年は,親子関係の密着化が見られ,青年期から成人期に移行する年齢が上がっていると言われています。そうした背景を踏まえ,親から独立しようとする分離行動の有無のみだけでなく,その背景にある,親に対し「良い子」であろうとするといった,親に対する過剰適応の高さの違いによって,こどもの自己決定の在り方がどのように変わるのかということを検討しています。また,インタビュー調査も実施し,親に対する過剰適応を抱えてきた方々がどのような葛藤や認知の変化を辿りながら,自己決定をしてきたのかというプロセスについて検討しています。
学部と大学院とで大きく違うと感じることは何ですか。
実践的で専門性の高い学びが得られる点です。学部では座学も多いですが,大学院では授業においてもケースについて話し合ったり、面接のロールプレイを行ったりといった主体的な姿勢が求められます。また,実習を通して,実際のケースと深く関わることができたり,そのケースについて,多くの経験を積んできた先生方から助言をいただけたりすることは,大学院でしかできないことだと実感しました。
印象に残っている授業を1つ教えてください。またそれはなぜですか。
事例検討を行う授業です。学内の相談室でのケースや,実習先で関わったケースについて,大学院生と先生が見立てや方針について意見を出し合って検討を行います。継続してケースを行う中で,一つの視点に囚われてしまったり,自分の向き合い方を客観的に見ることが難しくなってしまうことがありますが,この授業では,様々な質問や意見が自由に飛び交うので,そこでケースや自分の見方を振り返ったり,新たな視点を得られ,より豊かな見立てに繋げることができます。
大学院生活について教えてください。
1年生では,授業が多く,実践に向けた準備を行います。先輩方が行っている相談室のケースについて事例検討を行うことに加え,面接やアセスメントの演習や,各領域の知識や技能について学びを深めます。2年生になると,授業はほとんどなく,各自でスケジュールを管理しながら実習を行います。学外実習では,医療・福祉・教育といった様々な領域の機関に訪問し,現場の方から指導を受けながら,心理的支援やアセスメントの経験を重ねます。また,1年生の後期ごろからは,学内の心理教育相談室および発達支援相談室でカウンセリングの実習を行います。子どものプレイセラピーや保護者面接,個人面接といった様々なケースを担当するため,幅広く経験を積むことができます。また,実習先では検査を実施したり,相談室では出会わないような様々なケースに出会うため,自ら学びを深めたりすることも必須です。そのため,実習がない日は院生室で勉強したり,実習に向けた準備をしたりしています。 毎日忙しい日々を過ごしていますが,休息もケースと向き合うためには必要だと思います。院生はそれぞれでスケジュールを管理しながら,遊びに出かける時間も計画を立てて作っています。
入学を考えている方へのメッセージをお願いします。
院生生活は,タスクも非常に多く,またケースや実習には責任と高い専門性が求められるため,肉体的にも精神的にも大変ではありますが,毎日のように院生同士でケースや実習,検査などについて教え合い,話し合いながら,お互いを高め合う時間は,私にとってとても充実したものになりました。これから心理職を目指す皆さんも,大学院でのかけがえのない2年間を過ごせることを願っています。
日本型教育グローバルコース
日本型教育グローバルコース 令和2年度入学 WANG XINYE(オウ シンヨウ)さん
愛知教育大学大学院に進学した理由を教えてください。
教育学が専攻できる大学をいろいろと検討しましたが、現在の指導教員との出会いのほか、愛知教育大学大学院であれば自分の興味や専門領域をより深めていける学習環境があるとことがわかり、まずは研究生として入学してから修士課程に進学することを決めました。
研究テーマを教えてください。
多文化教育の日中比較研究です。多文化教育について、母国であり多民族国家の中国と異文化を積極的に受入れる日本を対比してみると面白いのではないかと考えました。授業の進め方や具体的にどのような教育活動が行われているか、考え方の相違点などにも注目しながら研究を進めています。
印象に残っている授業を教えてください。
最も印象に残っている授業は、授業視察のため附属幼稚園や高校を訪問し、学校教育現場での取組みを直に学んだことです。
授業がない時間帯や休日はどのように過ごしていますか。
中国で暮らす家族とWeChatで話したり、同じ宿舎に住む他大学の留学生達と一緒に出かけたりしながら気分転換をするほか、アルバイトもしています。また、奨学財団主催のイベントに参加することも楽しみのひとつです。
愛知教育大学での留学生活について教えてください。
研究生として入学後は、チューター制度を利用しました。日本語教育を専攻する学部生チューターと週1回のペースで会い、コミュニケーションを深めることで、愛知教育大学での留学生活に馴染んでいきました。
大学院生になってからは、文献探しや論文を書くため、附属図書館を利用することが増えました。指導教員を含め周囲のサポートがあり、研究を順調に進めることができています。

日本型教育グローバルコース 令和2年度入学 LE THI TRANG(レ ティ チャン)さん
愛知教育大学大学院に進学した理由を教えてください。
私がベトナムの大学に通っていた頃、国際交流活動のためベトナムの大学を訪問中のある日本人高校生に出会いました。当時、私は学部3年生でしたが、日本からやってきた若者が、将来の夢や自分の考えを堂々と話す姿がとても印象的でした。
この日の出会いをきっかけに、私自身も自分の軸をしっかり持って、自らの人生を切り開いていけるよう成長したいと思うようになり、大学卒業後は日本への留学を目指すようになりました。
また、若者のキャリア教育について研究できる日本の大学院を探していたところ、愛知教育大学大学院を知り、進学を決意しました。
愛知教育大学での留学生活について教えてください。
まずは、研究生として愛知教育大学に入学しました。日本人学生と共に授業を受けたり、大学院進学に向けて指導教員に研究の相談をしたりしながら、愛知教育大学での留学生活にも徐々に慣れていきました。
大学院進学後は、課題や研究のため一人で集中して取り組む時間が増えたことは、研究生の頃との大きな違いだと感じています。
授業がない時間帯や休日はどのように過ごしていますか。
運動や料理などをして、リラックスする時間を持つようにしています。またオンラインで学外のキャリアコンサルタント養成講座を受講することにもチャレンジしました。
飲食店でのアルバイトでは、世代の異なる日本人と一緒に働きながら交流も楽しんでいますし、ハローワークでのアルバイトでは、主にベトナム人の求職活動を支援しています。
日本型教育グローバルコースへの進学希望者にメッセージをください。
入学後は何も心配することがないくらい大学でのサポート体制が充実しています。その分、入学するまでにしっかりと日本語の勉強をしておくことをおすすめします。

日本型教育グローバルコース 令和3年度入学 SITAULA BIBITA(シタウラ ビビタ)さん
愛知教育大学大学院に進学した理由を教えてください。
来日後に入学した大学の進路指導教員の勧めがあり、愛知教育大学について調べたところ留学生専用のコースがあることを知り、愛知教育大学大学院への進学を決めました。また、外国人教員が在籍しているため、いろんなことを相談しやすく心強いと感じたほか、多様な文化的背景を持つ留学生と共に学べる環境に魅力を感じました。
研究テーマやキャリアプランについて教えてください。
私の研究テーマは、ネパールでの教育現状と日本型教育普及の検討です。教職に就く兄姉などの影響もあり、私も次第に教育に関心を抱くようになりました。大学院修了後は日本での就職にも興味がありますが、いずれは母国であるネパールに帰国し、ネパールの教育をより良くする活動や仕事に就きたいと考えています。
愛知教育大学での留学生活について教えてください。
学部とは違い大学院では、主体的な活動や行動が求められると感じています。さまざまなことに対して興味・関心を拡げつつも、何を学びどのように研究を進めていくかを自己責任で決定していくため、しっかりしなくちゃいけないなと思っています。
日本型教育グローバルコースへの進学希望者にメッセージをください。
外国人留学生が対象のコースですが、日本人学生と共に学ぶ授業を選択することもできるため、さまざまなことを学べて面白いです。また、外国人留学生の受入れ体制が充実していて、国際交流活動も盛んです。安心した留学生活を過ごせる環境があるため、日本型教育グローバルコースへの入学をおすすめします。

日本型教育グローバルコース 令和5年度入学 RAHMAN MD TAREK(ラハマン エムディ タレク)さん
愛知教育大学大学院に進学した理由を教えてください。
私は自国の大学において、日本言語文化学科で学士課程を修了しました。バングラデシュのダッカ大学(University of Dhaka)では、2017年に初めて日本語専攻の学科が開設され、私はその第1期生として学びました。在学中、日本語教師としての専門性を高めたいと考えるようになりました。
学部生時代の教育実習や、アルバイトとしての日本語教師の経験、在バングラデシュ日本大使館でのボランティア活動、さらにはバングラデシュ日本語教師会(JALTAB)での研修を通じて、私は自身の教育観の多くが、自らの学習経験によって形成されていることに気付きました。しかし、バングラデシュの日本語教育により貢献するためには、日本の大学院で専門的な教育を受けることが必要であると考えました。そこで、日本の教育系大学について調査を進めた結果、愛知教育大学は教員養成を専門とする大学であり、私の志向に最も適した環境であると判断しました。そのため、愛知教育大学大学院への進学を決意しました。
研究テーマについて教えてください。
学部時代は日本語を専攻していたため、日本語教育に関連する研究を行いたいと考えました。その中で、バングラデシュの日本語学習者が敬語の習得において多様な困難を抱えていることに気付きました。さらに、バングラデシュにおける日本語教育では、敬語に関する研究が十分に行われていないことも明らかになりました。そこで、バングラデシュの日本語学習者がより効果的に敬語を学べる教授法を探求するため、「より適切な敬語教授法の提案―バングラデシュ人日本語学習者を対象に―」を研究テーマとして設定しました。本研究を通じて、バングラデシュの日本語学習者のみならず、南アジアをはじめとする世界中の日本語学習者にも貢献できると考えています。
印象に残っている授業を1つ教えてください。またそれはなぜですか。
愛知教育大学大学院の授業を通じて、日本語に関する知識をより深めることができました。また、日本における日本語教育のみならず、海外の日本語教育についても学ぶ機会がありました。その中でも、特に印象に残っているのは「探究型カリキュラム・教材の開発とグローバル」という授業です。この授業では、日本語に関する既存の知識を整理するとともに、新たな知見を得ることができました。さらに、自身が誤解していた点についても明確に理解し直すことができ、日本語教育に対する視野が広がったと感じています。
愛知教育大学での留学生活について教えてください。
私は研究生として愛知教育大学に入学しました。日本人学生とともに授業を受ける中で、日本の教育環境に徐々に適応し、大学院進学に向けて指導教員と研究相談を重ねることで、自身の研究分野についてより深く理解を深めることができました。その過程で、愛知教育大学での留学生活も次第に充実したものとなりました。また、日本語教育を専攻する学部生によるチューター制度は、学習面や生活面で困った際に非常に役立ちました。大学院進学後は、文献調査や論文執筆のために附属図書館を頻繁に利用するようになり、指導教員をはじめとする多くの先生方のサポートを受けながら、研究を順調に進めています。さらに、国際交流センターを通じて日本人学生との交流の機会が増え、多様な経験を積むことができました。また、附属学校との交流を通じて日本の学校環境について学ぶ機会も得ました。特に、外国人児童生徒支援リソースルームでは、母国語であるベンガル語の勉強会を開催することができ、大変貴重な経験となりました。
このように、愛知教育大学での留学生活は、研究活動だけでなく、学業以外の活動にも恵まれ、非常に有意義なものとなりました。
授業がない時間帯や休日はどのように過ごしていましたか。
授業がない時間帯や休日は、主に研究課題に取り組みながら、日本各地の世界遺産や観光地を訪れ、登山を楽しむなどの旅行をしました。また、日本の伝統文化を体験する機会も積極的に持ちました。さらに、家族と連絡を取り合い、日本での経験を共有する時間も大切にしました。
日本型教育グローバルコースでの経験が進路決定にどのように生かされたのかを教えてください。
日本型教育グローバルコースを通じて、日本の教育制度や教授法について体系的に学ぶことができました。特に、日本語教育における教授法の理論と実践のバランスを重視したカリキュラムは、研究テーマである「より適切な敬語教授法の提案」に対する理解を深める重要な要因となりました。また、多様な国籍の学生や教育者との意見交換を通じて、日本型教育の特性やその国際的適用可能性について考察する機会を得ました。これらの経験は、愛知教育大学大学院博士課程への進学および今後の研究活動、さらには将来の日本語教育に携わるうえでの指針となり、進路決定に大きく寄与しました。
入学を考えている方へのメッセージをお願いします。
愛知教育大学大学院は、日本語教育をはじめとする教育分野において、理論と実践の両面から学びを深めることができる環境が整っています。特に、日本型教育グローバルコースでは、多様な教育制度や教授法について学び、異なる背景を持つ学生や研究者と意見交換を行うことで、教育に対する視野を広げることができます。また、指導教員や学内のサポート体制も充実しており、研究活動に専念できる環境が整っています。日本語教育や教育学分野での専門性を高めたい方にとって、非常に有意義な学びの場となるでしょう。ぜひ、愛知教育大学での学びを通じて、自身の研究を深め、将来の教育に貢献していってください。

日本型教育グローバルコース 令和6年度入学 VO TRONG THI(ウォー チョン ティ)さん
愛知教育大学大学院に進学した理由を教えてください。
私はベトナムのハノイ国立教育大学を卒業しました。同大学は愛知教育大学の協定校であり、両大学間の交換留学プログラムを通じて愛知教育大学を知りました。3年生の時、初めて日本を訪れる機会があり、この大学に親しみを感じました。愛知教育大学国際交流センターのスタッフや出会った先生方のおかげで、再びここで学びたいという夢を持つようになりました。そのご縁で、愛知教育大学で大学院の勉強をする機会を得ることができました。
研究テーマについて教えてください。
私にとって日本文化は、子供の頃から漫画を通じて特別なものでした。日本文化が大好きで、研究テーマは日本の宗教文化です。具体的には、日本の神道と仏教、そしてそれらが学校教育に与えた影響について研究しています。例えば、江戸時代に農民に教育を提供した寺子屋や、現代の神道系学校などです。
印象に残っている授業を1つ教えてください。またそれはなぜですか。
多くの授業が私に大きな印象を残しました。大学院生の先生たちは、私たちが勉強している間、いつも全力を尽くして私たちを助けてくれます。マイヤー・オリバー教授の教育授業はおそらく私たちが決して忘れることのないクラスです。その科目を通じて、ドイツ、日本、中国など、多くの国の教育について学びました。これまで、世界中の国々のこれほど多くの教育システムにアクセスしたことはありませんでした。それは、日本の教育だけでなく世界の他の国々についても多くのことを理解するのに役立ちました。
愛知教育大学での留学生活について教えてください。
日本での生活を始めた当初は、大変なことばかりでした。私も最初はカルチャーショックを受けました。しかし、愛知教育大学国際交流センターには大変お世話になりました。日本の日常生活文化についてすべて教えてもらいました。ゴミの分別から地震対策まで、生活の些細な事からお手伝いして頂いております。その後、私は日本の生活に適応し、物事が楽になりました。
入学を考えている方へのメッセージをお願いします。
このコースは私の青春時代で最高のものです。教育上のキャリアに役立つ知識を得ることができました。それに、世界中から来た友達と交流できる環境もあります。まだ迷っているなら、信じてください、コースを受講することが最善の決断になるでしょう。

教育ガバナンスキャリアコース
教育ガバナンスキャリアコース 令和3年度入学 尾潟 祐介さん(豊橋市役所 教育委員会 教育政策課)
私は自治体職員として本大学院に在籍しています。多文化、情報教育、地域協働など、教育行政を取り巻く環境は日々急速に変化しており、いずれも高度な専門性を求められる領域となっています。私は「地域とともにある学校づくり」いわゆるコミュニティ・スクールを自治体に導入したいと思い研究を行っていますが、コミュニティ・スクールに限らず、教育政策の立案は、自治体の各種計画や財務状況といった「自治体の視点」だけでなく、学校経営やカリキュラムといった「学校現場の視点」の理解が不可欠です。
教育ガバナンスキャリアコースでは自治体及び学校現場について、基礎から最新の状況を学ぶことができます。院生の方々も学校事務職員や教職員と多様な方が在籍しており、それぞれが相互補完しながら授業が展開されるため不安になることもありません。本大学院で身に付けたことを自治体に持ち帰り、実践するために頑張っています。 (令和3年度現在)

教育ガバナンスキャリアコース 令和3年度入学 鈴木 美穂さん(豊田市役所 教育委員会 教育政策課)
私は、自治体からの派遣職員として、本大学院に入学しました。もともと教育や子ども関係の施策に興味があり、教育行政のスペシャリストを希望していました。より専門的な知識を身につけ、本市の教育行政に少しでも役立てれば...と思い、本大学院を志望しました。
大学院では複式学級をテーマに研究を進めたいと考えています。少子高齢化が進む中、子どもたちにとって本当に良い教育環境とは何なのかを明らかにしていきたいです。久しぶりの大学生活に当初はとまどうこともありましたが、新しい知識を吸収する時間がとても充実した日々になっています。授業では講義を聞くだけではなく、グループワークや発表、調査など、自ら調べ、学び、議論を行う時間が多いです。職種や年齢が異なる大学院の同期の皆さんと交流することで、多くの刺激をもらい、成長することができると思います。(令和3年度現在)

教育ガバナンスキャリアコース 令和3年度入学 上村 友太さん(名古屋市教育委員会 教職員課)
愛知教育大学大学院に進学した理由を教えてください。
私は、市立学校の学校事務職員として勤務しています。これまでの職務を通じて、実務に密接に関連する教育制度にも関心を持つようになり、学校事務を教育行政と一体として捉える視点が重要だと感じるようになりました。そのような視点をさらに深めるための場を探していた際、ちょうど当コースの設置を知り、これを学ぶ絶好の機会だと思い進学を決意しました。
研究テーマについて教えてください。
保護者や地域住民が学校運営について協議を行う仕組み、コミュニティ・スクールについて研究を行いました。コミュニティ・スクールでは、学校と地域の双方が当事者意識を持ち、対等な立場で協議などに臨むことが鍵になると考えています。私の研究では、コミュニティ・スクールの先行事例がある自治体において、教員以外の関係者がどのように意識を変化させたのか、その要因と経緯を調査し、コミュニティ・スクールの力点が、「地域による学校支援」から「対等な立場での学校づくり」へと変化するために必要な取り組みについて検討を行いました。
印象に残っている授業を1つ教えてください。またそれはなぜですか。
「学校のガバナンスとマネジメント」という授業が特に印象に残っています。この授業は、教育政策・教育行政の変遷や、学校運営に関連する重要な概念について学ぶものでした。当時、私にとっては理解が追いつかない部分もあり、授業中に悔しい思いをしたことをよく覚えています。しかし、その悔しさが学びを深めるきっかけとなり、自分の意欲を一層高めることになったと感じています。
仕事との両立について教えてください。
勤務後の夜間や週休日に授業が設定されていたため、スケジュール管理は比較的容易だったと思います。ただし、仕事の繁忙期や修士論文の執筆時期には慌ただしく感じることもありました。それでも、どちらか一方を理由にもう一方を疎かにすることは避けたかったため、両立できるように努力しました。
修士課程で得られたことは何ですか。
修士課程の授業や研究を通じて、同期を始めとする様々な立場の方々とディスカッションや交流を重ねる中で、私が持っていた教育に対する認識が一面的なものであったことに気づかされました。学校現場や政策立案者といった特定の立場だけでなく、教育に関わる多様な視点が存在することを、実務に携わる一職員としても深く理解し、それらを適切に整理して実践に繋げていくことが、教育政策を効果的に実施するために重要であると学びました。
修士課程で学んだことは仕事にどのように活かされていますか。
現在、縁あって一時的に教育委員会事務局で勤務しており、他の行政職の方々と協力しながら仕事を進めています。そこでは学校事務職員としての現場の知識や経験に加え、修士課程で学んだ教育行政に関する見識を活かすことを心がけており、そのおかげで相互理解が深まり、共通の認識を得るのがスムーズになっていると感じています。
入学を考えている方へのメッセージをお願いします。
ここ数年で、学校や学校事務職員に求められる役割は大きく変化しています。現場では、これまでとは異なる職員や関係者と関わる機会が増え、新たな課題に対応することも多くなっているのではないでしょうか。このような環境の中で、学校事務職員として、目の前の子どものウェルビーイング向上に貢献するためには、教育に関する知識や認識をより広く、深くアップデートしていくことが非常に有効だと考えます。ぜひ、新しい学びに踏み出してみてください。

教育ガバナンスキャリアコース 令和5年度入学 大杉 秋乃さん
愛知教育大学院に進学した理由を教えてください。
教育行政について深く学びたいと思ったからです。学部生時代に、地域教育に興味をもちました。その中で次世代型教育・学校づくりをリードする教育行政職を養成する本コースで、自治体の教育政策について学びたいと思い、学内進学し、本大学院に入学しました。また、現職の自治体職員や学校事務の方と関わりながら、教育・学校現場の現代的課題に向き合えるところにも魅力を感じました。
研究テーマについて教えてください。
地域学校協働本部による地域資源の活用が主なテーマです。学校と地域をつなぐ地域コーディネーターの役割や意識に着目し、どのように地域資源が活用されているのかを調査し、学校と地域の連携・協働のあり方について研究しています。
印象に残っている授業を1つ教えてください。またそれはなぜですか。
「教育政策の分析と戦略立案」です。この授業では、国や自治体の教育政策を比較し、各自治体の強みや弱みを把握した後に,新たな政策提言を行いました。教授や他の受講生から意見をいただきながら、新たな気付きや学びを得ることができました。
大学院生活について教えてください。
基本的には平日の夜間に対面とオンラインのハイブリット型で授業が行われます。受講人数は少数であるため、じっくりと教授や他の受講生と意見交換することができます。
入学を考えている方へのメッセージをお願いします。
教育ガバナンスキャリアコースでは、何といっても居住地も職業も異なっている方々と一緒に学べることが魅力だと思います。私は、学内進学だったため、不安もありましたが、皆さん優しく、それぞれの立場から意見をいただき、多くのことを学ばせていただきました。また、授業で受講生の関心に合わせた内容を取り上げてくださるなど,先生方も親身になってサポートくださいました。2年間の学びを通して自分自身が成長できたため、私は本大学院に進学してよかったと思います。