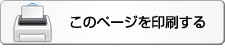ここからコンテンツです。
2025年8月26日 愛知県ユネスコスクール指導者研修会を開催しました。
2025年09月11日
8月26日(火)午前に愛知県生涯学習推進センターで「愛知県ユネスコスクール指導者研修会」を開催しました。本学は「ユネスコスクール支援大学間ネットワーク(ASPUnivNet)」に加盟し、愛知県・三重県のユネスコスクールを支援する活動を行っています。本研修会はユネスコスクール間のネットワーク作りを支援することや、未加盟校へのESD活動の取り組みのきっかけづくりとすることを目的に毎年開催しています。今年度も愛知県教育委員会が主催する「ESD・SDGs推進指導者研修会」との同日開催となりました。
研修会に先立ち、本学の杉浦慶一郎連携・附属学校担当理事が開会のあいさつを行いました。杉浦理事は「学校での困りごとに対し、事例発表とディスカッションが有意義になるとうれしい」と本研修会への期待を述べました。
 実践事例発表の様子
実践事例発表の様子
実践事例の発表では県内外のユネスコスクール先進校4校より発表があり、本学附属名古屋小学校の山田泰弘教諭、金沢市教育委員会学校指導課の榎木洋平指導主事、本学附属高等学校の山本真生教諭、京都府立嵯峨野高等学校の岡本領子教諭が、それぞれの学校や教育委員会での取り組みについて紹介しました。
本学附属名古屋小学校からは日常の授業を通じてESDにつなげる実践、金沢市教育委員会からは校種を越えた実践発信やネットワークづくりの取り組み、本学附属高等学校からは部活動を基軸としたSDGsへの参画、京都府立嵯峨野高等学校からはカリキュラムデザインに紐付いたESDの実践などが発表されました。
 ディスカッションする事例発表者
ディスカッションする事例発表者
実践事例の発表後、本学地域連携センター岩田吉生副センター長の司会のもと「普段の授業をどのようにしてESDとして展開していくか」をテーマに実践発表者によるディスカッションを行いました。岩田副センター長からの問いかけに対し、実践発表者からはカリキュラムにSDGsの目標を紐付けるアプローチや、児童生徒の学びのために教員同士が学び合う手法などが紹介されました。岩田副センター長は「子どもたちが本当に学んだのであれば、問題意識が他人事から自分事に変化する。その中で、他者とのかかわり方などの行動が変わっていく姿を見守ることが大切」と述べました。
最後に大鹿聖公地域連携センター長が閉会のあいさつを行い、「先生がやらせる形ではなく、子どもたちがやりたくなるような形で取り組んでいけると良い。ESDのために何か特別なことをしなければいけないのではと思われがちだが、日常の授業を通じて子どもたち自身で正解を見つけていけるような支援を行っていただきたい」と総括しました。
(地域連携課地域連携係 主任 柘植貴史)
ここでコンテンツ終わりです。