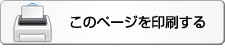ここからコンテンツです。
2025年8月22日 理科観察実験指導力向上セミナーを開催しました。
2025年08月29日
8月22日(金)に、本学自然科学棟で、小学校教員の方々を対象に、理科の観察・実験授業の指導方法について研修するための「理科観察実験指導力向上セミナー」を開催しました。このセミナーは本学理科教育講座の教員が講師を務め、公益社団法人日本理科教育振興協会が主催し、本学が共催にて実施しています。小学校教員を対象としたセミナーは今年で13回目を迎えますが、今年度は初めて、教員の卵である本学学生にもこのセミナーを開放し、希望した6人の学生も現職教員と共にセミナーを受講しました。
生命(生物)分野の講座では、加藤淳太郎教授が講師を務め、顕微鏡の使い方の基礎と維管束細胞の観察と題して、ニンニクの芽とパセリの維管束細胞の観察を行いました。始めに組織が観察しやすいように茎を薄くスライスする方法として、絆創膏で手を保護する実験ハックが紹介されました。その後、受講者は実体顕微鏡と光学顕微鏡でスライスした茎を観察するとともに、道管・師管の様子を写真に収めていました。現職教員の受講者からは染色液に利用できる入手しやすい材料や観察に適した植物など、実際に観察実験を行った経験を踏まえ、いかに実践を行いやすくできるかを想定した質問がありました。また、これまでは、現職教員向けの本セミナーと学生を対象とするプレ教員セミナーを別に実施していましたが、両者を対象としたことで普段、大学の備品である顕微鏡を利用している学生が操作の仕方を現職教員に教える場面も見られ、今後教師となる学生にとっても同僚性を育むよい機会となりました。
 加藤淳太郎教授実験ハックを披露
加藤淳太郎教授実験ハックを披露
 顕微鏡での観察を写真に記録
顕微鏡での観察を写真に記録
 ふりこ実験の注意点を確認
ふりこ実験の注意点を確認
エネルギー(物理)分野では、岩山勉理事が講師を務め、電気・電流・電磁石単元の完全理解とふりこの運動を題材としました。ふりこの長さの測り方や往復する時間をどのように測るとブレが少なくなるかなどを確認しつつ、実験を行いました。 教員が授業の内容によってアナログとデジタルをうまく使い分け、組み合わせて、児童生徒の興味関心を引き出し、効果的な理科授業が実現できるように、科学・ものづくり教育推進センターの活動を継続してまいります。
(地域連携課地域連携係長 松本典江)
ここでコンテンツ終わりです。